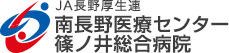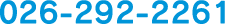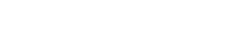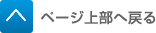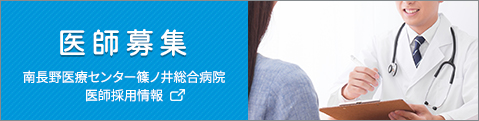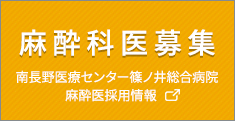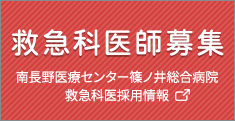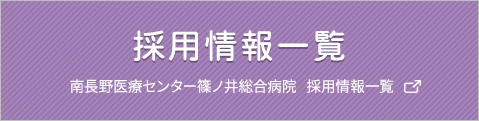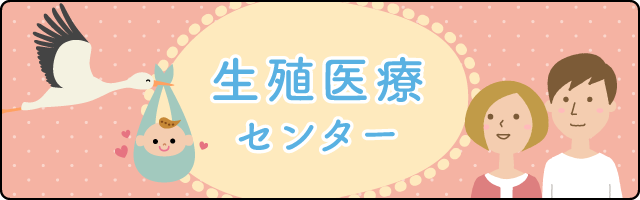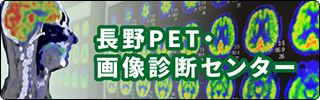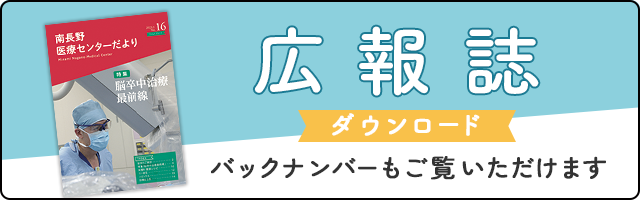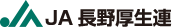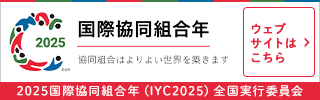ロボット手術センター
診療科の特徴
ロボット手術は、基本的にこれまで腹腔鏡で行ってきた手術を、関節機構を備えたロボット支援機器と高精細3D視野を用いて行う低侵襲手術です。一部の術式では、従来は開腹で行っていた手術をロボットで安全に実施している場合もあります。開腹手術や腹腔鏡手術と比べ、患者さんの体への負担をいっそう少なくできる可能性があります。
本邦では2012年に前立腺がん手術から保険適用が始まり、その後適応が拡大しましています。泌尿器科では前立腺・膀胱・腎臓・副腎など、さらに消化器外科・婦人科・呼吸器外科・心臓血管外科・耳鼻咽喉科でもロボット支援手術が広がっています。長野県内では現在9施設に導入され、当院では2025年2月からロボット手術を開始しています。
泌尿器科(前立腺)・消化器外科(胃・直腸)・婦人科(子宮・骨盤臓器脱)においてロボット支援手術を実施しています。今後も症例選択と安全性を最優先に、対象術式の拡大と質の向上に取り組みます。
ロボット手術の長所
・操作性:関節付き鉗子と手ぶれ補正、拡大3D視野により、繊細な縫合・剥離操作が安定
・低侵襲:創が小さく、痛み・出血・創感染・腸閉塞などの負担軽減が期待
・回復:歩行や食事再開、社会復帰までの期間が短縮される傾向
開腹手術との比較
・皮膚切開が小さく、創痛・創部合併症が少ない傾向
・出血量・輸血率の低減が期待
・在院日数の短縮、早期社会復帰
腹腔鏡手術との比較
・関節機構を備えた鉗子と3D視野で縫合・結紮の精度が向上
・深部・狭骨盤など取り回しの難しい部位で有利
・カメラ固定と視野の安定により、再現性・教育性が高い
・難症例での開腹移行率の抑制が期待
ロボット手術の短所
・導入初期は手術時間が長くなる傾向(経験の蓄積で短縮が見込める)
・機種によっては触覚フィードバックに乏しいため、視覚と経験に依存
・器機トラブル時の切替(腹腔鏡・開腹)体制の構築が必要
医師紹介
後藤 正博 (ごとう まさひろ)
2010(平成22)年卒
| 役職 | 泌尿器科副部長、ロボット手術センター長 |
|---|---|
| 資格 | 日本泌尿器科学会専門医・指導医 泌尿器腹腔鏡技術認定制度認定医 ロボット(da Vinci)手術認定医 泌尿器ロボット支援手術プロクター da Vinci(膀胱・前立腺) Rezumシステム認定医 |
| 専門分野 |
西村 良平 (にしむら りょうへい)
2008(平成20)年卒
| 役職 | 産婦人科副部長、生殖医療センター長、ロボット手術センター副センター長 |
|---|---|
| 資格 | 日本産婦人科学会認定専門医 日本生殖医学会生殖医療専門医 NCPRインストラクター J-MELSベーシックインストラクター 日本スポーツ協会公認スポーツドクター 母体保護法指定医 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医 日本DMAT隊員 |
| 専門分野 | 不妊症、骨盤臓器脱、腹腔鏡手術、災害医療 |
有吉 佑 (ありよし ゆう)
2012(H24)年卒
| 役職 | 外科医長、ロボット手術センター副センター長 |
|---|---|
| 資格 | 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医 ロボット支援手術施行認定資格(daVinci) ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター |
| 専門分野 |